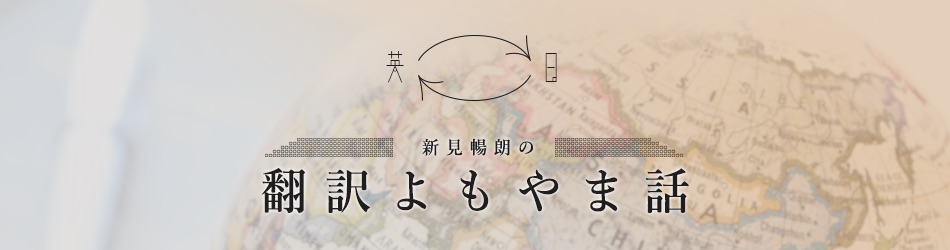
こんにちは。すっかり間が空いてしまいましたが、実践編として前回に続き「企業のプレゼンテーション資料の英訳」を取り上げます。一口に企業のプレゼンテーション資料と言いましても、様々な種類のものがありますから、前回同様、今回も「日本企業が投資家に自社の事業方針を説明する際に使うスライドを英訳する」というケースを想定し、その種のIRプレゼンテーションでよく使われる日本語のビジネス用語の訳語を考えてみましょう。
カタカナのビジネス用語には、「マーケティング」「ロジスティクス」「マネジメント」などのように、英訳する場合には元になっている英語(それぞれmarketing、logistics、management)をそのまま訳語として使って差し支えないものが多くあります。しかし、中には元の英語をそのまま持ってきたのでは、通じなかったり、誤解を招いたりするものもあります。それはカタカナのビジネス用語と元の英語が単純にイコールにならない、つまり意味のずれが生じているからです。意味のずれが生じるのは、カタカナ英語において、
ということが起こっているのが主な原因です。①から③までのケースについて、それぞれ代表的な例をあげます。
「リニューアル」は「製品をリニューアルする」「店舗をリニューアルする」「ホームページをリニューアルする」という形で、企業のプレスリリースやIRプレゼンテーションでよく目にします。いずれも「以前からあったモノの中身や外観を新しくする」という意味で、すっかり日本語として定着していますね。
ところが、「製品(店舗、ホームページ)をリニューアルする」を英訳する際に、「リニューアル」の元の英語である「renewal」や、その動詞形「renew」を使うことはできません。「renew」の定義は
だからです。強いて言うと、このうちの「傷んだり古くなったりした物を新しい物に取り替える」が意味的には日本語の「リニューアルする」に近い気もしますが、「製品や店舗のリニューアル」は壊れたり、古くなったりしたから替えるわけではありません。
では、日本語の「リニューアルする」を英語で正しく表現するにはどうすれば良いかと言いますと、以下のように新しくする対象によって動詞を使い分ける必要があります。
それぞれ実際の使用例を一つずつあげておきますと、
【製品のリニューアル】
Apple refreshed its MacBook Pro lineup this week with Intel's seventh-generation Kaby Lake processors and faster standard graphics options from Intel and AMD.
(https://www.macrumors.com/2017/06/08/2017-vs-2016-macbook-pro-tech-specs/)
【店舗のリニューアル】
Some time ago, the J. C. Penney Company remodeled its leading stores in 31 major markets to attract an upscale shopper.
【ホームページのリニューアル】
Access Hardware Supply has redesigned its Web site to make it easier for visitors to access the latest information on the company’s products, services and more.
「ダイバーシティ」もこのところよく目にするビジネス用語の1つです。その元になっている「diversity」は「多様性」という意味でしたが、米国では、1964年にCivil Rights Act(公民権法)が成立し、1972年にはEqual Employment Opportunity Actが改正され、雇用における人種や皮膚の色、性、宗教に基づく差別が禁止されて以来、「diversity」は特に「職場が多様な人材で構成されている状態」を意味するようになりました。
日本では「ダイバーシティ」は当初「女性活用、障害者雇用、高齢者雇用」などの狭い意味でとらえられることが多く、どちらかと言うと「女性管理職比率」や「従業員に占める障害者の割合」などの数値指標が注目されていました。最近では、そうした単なる数合わせではなく、「多様な人材を採用し、組織として受け入れ、その活躍を支援し、それを定着させること」に取り組む企業が増えてきています。それに伴い日本語の「ダイバーシティ」という言葉の意味も、当初の「職場が多様な人材で構成されている状態」というものから一歩進んで、「多様な人材を受け入れ、支援し、定着させる」というものに変わってきています。多様な人材がいるだけでなく、それが組織の中に自然に溶け込んでいる状態ですね。
ところが英語の「diversity」はあくまで「職場が多様な人材で構成されている状態」を意味し、「受容、支援、定着」といった意味合いは含まれません。その「受容、支援、定着」を表す言葉として「inclusion」があります。そしてその2つをワンセットにして「diversity and inclusion」というフレーズで使われることが多くなっています。
ですから、日本語の「ダイバーシティ」を単純に「diversity」と訳すのではなく、その取り組み内容によっては「diversity and inclusion」としないと、その実態が正しく伝わらないことになります。この「diversityの先にinclusionがある」という考え方を踏まえた文章がありましたのでご紹介します。日本でも『フラット化する世界』(The World Is Flat)などの著書で知られるThomas L. Friedmanの近著で、急速な技術革新の功罪について述べた『Thank You for Being Late』の一節で、ここでは職場の話ではなく、著者が生まれ育ったコミュニティが昔からマイノリティーの受け入れに熱心に取り組んできたことを語ったくだりです。多様な人々を一つのところに集めただけではだめで、お互いが異なる人種や考え方を受け入れ、尊重し合うことが必要だと述べています。
In and between the lines of these letters, there is not only an affection for this place we all called home but also an appreciation for the fact that the community that emerged from this mix of cultures didn't happen by accident—we were blessed with extraordinary local and state leaders, school principals, and parents, who time and again made decisions about the kind of inclusive place they wanted to build and who fought for those values against, at times, entrenched opposition. Pluralism doesn't just happen because diverse people are thrown together ... but in time they built a community that became unusually welcoming for its era to misfits, different ideas, and different people with funny accents.
(Thomas L. Friedman: Thank You for Being Late, 2016)
日本で今もっとも人気のあるビジネス用語の1つが「ゲームチェンジャー」ではないでしょうか。企業が打ち出す戦略や発売する新製品がいかに斬新かを表す言葉が「ゲームチェンジャー」です。
英語の「game changer」は、元々はアメリカンフットボール用語で、「試合の流れをがらりと変えてしまう選手またはプレイ」を指して使われていました。それが転じて、Merriam Webster Onlineの定義にある「A newly introduced element or factor that changes an existing situation or activity in a significant way」(現状を大きく変えてしまう新たな要素)という意味で使われるようになりました。また特にビジネス用語としての「game changer」には、同サイトは「A game changer is a person or thing that radically changes an industry or a company.」(業界や会社で地殻変動を起こす人やモノ)という定義を与えています。また形容詞形の「game-changing」も「現状を大きく変えてしまうほどのインパクトがある」という意味で使われます。
私が「game changer」という言葉を初めて耳にしたのは米国に駐在していた2000年頃で、当時勤務していたメーカーから業界初の新製品がいくつか発売され、それらをフィーチャーした広告キャンペーンを展開することになりました。そのキャンペーンのアイデアを広告代理店が提案してくれた際に、「これらの製品をgame changerと位置づけ...」という説明があり、面白い表現だと思った記憶があります。その後も様々な場面で「game changer」という言葉を見聞きしました。この言葉が最も声高に叫ばれたのは2008年の米国大統領選挙で、オバマ氏が黒人初の大統領に選ばれたときではなかったでしょうか。その時からでも、もう10年近く経っていますから、米国では「game changer」の言葉としての鮮度は落ちてきていると言えます。今でも米国で出ている新聞や雑誌ではときどき目にするものの、以前ほどの新鮮な響きはありません。
一方、日本で「ゲームチェンジャー」という言葉がビジネスの世界で広く使われるようになったのは比較的最近のことです。本家の米国ではすでに流行のピークを過ぎた「game changer」が、日本ではまさに流行のピークを迎えつつあります。さらに、先にご紹介したWebsterの定義にもあるように、「game changer」は相当大きなインパクトを持つ「もの」や「こと」を指すのに使う言葉であるのに対して、日本では目先を少し変えた新製品や、ちょっとだけ目新しい取り組みまでも「ゲームチェンジャー」と称するようになってきており、言葉のインフレが進行中です。当の企業からすれば、すべての新製品が「画期的」であり、すべての戦略が「革新的」なのでしょうが、それを日本語で「ゲームチェンジャー」と称し、その訳語としてそのまま「game changer」または「game-changing」を当てるのはやはり無理があります。「えっ、それがgame changerなの」という反応が返ってくる可能性があります。
本当に画期的で、業界の勢力図を一夜にして塗り替えてしまうような新製品であれば「ゲームチェンジャー」を日本語のIRプレゼンテーションで使っても差し支えないでしょうが、そういう場合でも、英語版資料では、鮮度の落ちた「game changer」や「game-changing」を使う代わりに、意味の強い順に、
などをお薦めいたします。
英語の「synergy」は、元々は「体内の器官の共動作用」や「医薬品の相乗効果」を意味する科学用語でした。それが1970年代以降、「異なる製品を一緒にマーケティングすることで個別に売るより大きな売上を達成すること」「企業内で複数の事業部門が連携すること」さらに「他社との提携、協業、合併などでより大きな業績をあげること」という意味で広く使われるようになりました。私が米国に駐在していた1990年代は米国で同業種、異業種を問わず、企業の大型合併や提携が相次ぎ、そのプレスリリースでは合併・提携の狙いを説明する言葉として判で押したように「synergy」が使われ、まさに「右を向いてもsynergy、左を見てもsynergy」といった有様でした。しかしそうやって華々しく展開された大型合併や提携も、いざ蓋を開けてみると、異なる企業文化のぶつかり合い、経営方針を巡る考え方の違いなどから、期待された「synergy」が生まれるどころか、合併や提携が業績の足を引っ張り、合併・提携解消に至るケースも少なくありませんでした。そうしたことから、マスコミの取り上げ方もそれまでの「synergy礼讃」から「Synergy is dead(シナジーは終わった)」「Synergy is a myth(シナジーなんて幻想)」と否定的なトーンに変わり、それに伴い企業も「synergy」という言葉を敬遠するようになってしまいました。例えば、こんな記事があります。世紀の大型合併ともてはやされた、2001年のAOLとTime Warnerの合併が失敗に終わったことに関連した記事です。
Synergy became a dirty word at Time Warner after the disastrous merger with AOL in 2001. The marriage of traditional and new media orchestrated just as the first Internet bubble burst destroyed billions in shareholder wealth.
(New York Post, October 16, 2014)
今や「synergy」という言葉にはある種の「胡散臭さ」や「眉唾感」といったマイナスのニュアンスがつきまとい、今でも米国企業同士の合併や提携は行われているものの、その狙いを「synergy」という言葉を使って説明することは以前ほど多くありません。
一方、日本企業はいまだに「シナジー」という言葉がお好きなようで、企業グループ内のグループ各社間の連携を強化することを「グループシナジーの強化」と称したり、企業提携の目的を「市場でのシナジーの追求」と表現したりしています。日本語のプレスリリースやIRプレゼンテーションで「シナジー」というカタカナ言葉を使うなとは申しませんが、問題は、その英語版で「シナジー」をそのまま「synergy」と訳してしまうことです。先ほど述べた理由により、海外の方にあまりポジティブに受け取ってもらえない恐れがあるからです。
では、日本語の「シナジー」を「synergy」を使わずにどう訳すか。「相乗効果」は要するに「1+1=3」のことですから、それをそのまま表現すれば良いのです。
などが考えられます。「シナジー」という単語1つをこんなに説明的に表現するのかと思われるかもしれませんが、「synergy」は「相乗効果」という意味ではあるものの、実体がわかりにくく、漠然とした言葉です。そういう中身があるようでない単語で済ませるのではなく、個々の状況を踏まえて「何を実現するのか」をより具体的に表現した方が読み手に伝わります。
皆さんは「jargon」という言葉をご存じでしょうか。これは「ある集団や業界内で使われる専門用語」という意味ですが、含みとしては「門外漢には意味がよくわからない言葉を仲間内で使う」というものです。jargonの中には、最初のうちはある集団内だけで隠語のように使われていたものが、一般の人もごく普通に使うようになったものもあります。
political jargonは「政治用語」で、古くからあるものとしては、米国の二大政党である民主党のシンボルカラーがblue、共和党のそれがredであることから、民主党支持者の多い州を「blue state」、共和党支持者が多い州を「red state」、そして両党が拮抗している州を「purple state」と呼んだりします。また政治家は有権者をタイプ分けするのが好きで、環境保護論者を揶揄して「tree-hugger」(文字通りは「木にしがみついている人」)、子育てに忙しい郊外に住む白人女性を「soccer mom」、その派生形の「hockey mom」(共和党支持の母親)、「Wal-Mart mom」(節約志向の強い主婦)、保守的なブルーカラー男性層を「NASCAR dad」(NASCARは自動車レースのこと)と称します。こういったpolitical jargonを集大成したのが、「翻訳よもやま話」の第四回「辞書の選び方、使い方(中編)」でご紹介した『Safire's Political Dictionary』です。
スポーツの世界からも実に多くのjargonが生まれています。中でも米国で人気の高いフットボールや野球はjargonの宝庫です。今では「作戦計画」「戦略」という意味で使われる「game plan」は、元々はフットボールの試合で使われていたjargonでした。「ball game」は「野球」の別称ですが、「a whole new ball game」で「全く新たな展開」という意味になり、「hardball」は野球の「硬球」のことですが、「play hardball」というと「強硬手段をとる」「容赦しない」という意味になります。「pinch hitter」は元々の「代打」という意味が広がって、「代役」全般を指すようになりました。
ビジネスの世界でも、経営用語辞典や会計用語辞典に載っている「intellectual property」や「accounts payable」などのれっきとしたビジネス用語の他に、様々なbusiness jargonがあります。思いつくままにあげてみますと、
などがあります。ネットで「business jargon」を検索すると、これ以外にいくつもの言葉がリストアップされますので、チェックしてみてください。
こういったbusiness jargonは、日本人にとっては表現自体が面白かったり、何となく格好良く聞こえたりするので、つい飛びついてしまいがちです。しかし英語のIRプレゼンテーション資料ではこういったjargonは避けたほうが無難です。理由は、一つには意味が漠然としていたり、気取って聞こえたりすること、もう一つは言葉の鮮度の問題です。英語のbusiness jargonのライフサイクルを考えると、多くの場合、まず米国の広告代理店や経営コンサルタント、マーケッターなどがあるjargonを使い始めます。最初は新鮮に聞こえ、それに米国の一般企業やマスコミが飛びつきます。そうやってあちこちで使われるようになると次第に新鮮味が失せ、すっかり手垢のついた使い古された言葉になってしまいます。日本の企業が英語のIRプレゼンテーション資料で流行り言葉だと思って使うと、実は使い古された言葉だったということになりかねません。business jargonを避けて、例えば先にあげた「human capital」の代わりに「employees」や「staff」を、「think outside the box」の代わりに「think creatively to come up innovative ideas」と普通の言葉で表現すべきです。
英語のビジネス用語の「鮮度」や、それをカタカナ化したものと元の英語の「意味のずれ」は辞書を引くことである程度は掴めますので、翻訳の際には手間を惜しまず英和辞典、英英辞典、専門用語辞典などに当たってください。さらに辞書に当たるだけでなく、普段からビジネス用語に対する感度を養っておくことも大切です。ある英語のビジネス用語が一時的な流行語なのか、それとも定着した言葉として使って差し支えないのか、またその言葉がどういうニュアンスを持っているか、ネイティブスピーカーにどう響くか、といった語感を磨くには、以前にも申し上げたように、やはり活きの良い、良質な英文(週刊の英字ビジネス誌やニュース誌など)を継続して読むのが一番です。また、様々なビジネス系の英語サイトを閲覧し、米国人ライターの手になる記事の中で、あるビジネス用語がどう使われているかをこまめにチェックし、そこからニュアンスをつかみ取るということも有効なやり方です。
ということで、今回もプレゼンテーション資料の英訳をテーマに、そこで使われるカタカナ英語について、
代表例を取り上げました。今回取り上げた言葉以外にも該当するものがたくさんありますが、それは別の機会にご紹介したいと思います。次回もプレゼンテーション資料の英訳テクニックについてお話しするつもりです。
では、また。
翻訳会社ブレインウッズは、翻訳文書の使用用途別に翻訳サービスをご提供します。
契約書の翻訳、マーケティング・プレゼンテーション資料の翻訳、マニュアルの翻訳、プレスリリースの翻訳、
学術論文の翻訳、Webサイトの翻訳は、ぜひお任せください。
医療・医薬やIT・通信、金融、製造など、専門性の高い業種や分野に対応。
各分野の専門翻訳者と経験豊富なコーディネーターのチームがお客様のニーズに対応します。
海外取引やインバウンド向けのビジネスを展開する会社の皆さまをサポートします。